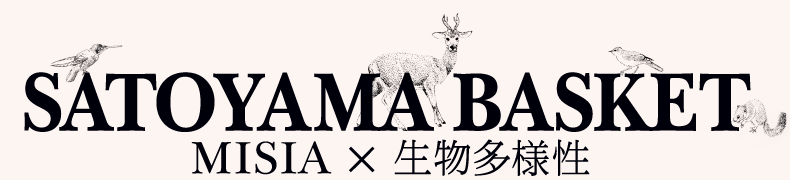今月の本 : 「人間はどこまで動物か」
人間はどこまで動物か。このエッセイ集のタイトルを前に、しばらく考え込んだ。
確かに人間は動物だよな。哺乳類だし、生物学から見た人間について、論じているのかな?
と、勝手な思い込みで読み始めたが、見事に裏切られた。それも良い意味で。
動物行動学者として、日本の第一人者であった日高サン(と尊敬の念と親しみを込めて、敢えて書かせていただく)は、人間を「ヒト」と言うようになったことで、人間も動物と認知されるようになったことを歓迎する。「人間」と「ヒト」が区別されることで、結果として人間と動物を区別しようという私たちの意識に警鐘を鳴らしている。
人間がほかの動物と違うように、犬だって、キリンだって、ゾウだって、ほかの動物と違う。その違いがなければ、生物多様性が失われてしまう。
日高サンが素晴らしいのは、すべての生きものへの優しい視線を失わないこと。そして安易な環境保護の意識、生物多様性という言葉にさりげなく警鐘を鳴らしていることだ。
エッセイのひとつに、蛍が飛ぶ川の話がある。
蛍が棲むために川をきれいにしなければならない。それはそうなのだが、きれいな川は澄んだ川とイコールではない。川の中に微生物がいなければ蛍のエサもないし、魚や虫が棲むこともできない。適度に汚れた川が、生きものにとっても棲みやすい世界になるのだ。その後のアフリカのカバの糞と川の魚をめぐる話には思わず笑ってしまった。
自然との共生の難しさを、身近な例で説明してくれるのも、日高サンのすごさだ(ちなみに日高サンは日本エッセイスト・クラブ賞を受賞されるなど、そのエッセイのうまさには定評がある)。
緑地化の名の下に木を刈り込み、雑草を抜いてしまう。最近ではガーデニングも人気だ。でも、ガーデニングで植えられている植物は外来のもの。日本の草木は「雑草」として切り取られてしまう。
日高サンの指摘で非常に考えさせられるのが、生物多様性という言葉のあいまいさだ。
私たちが、「生物多様性」というとき、命がつながり、尊重し合う様を想像するかもしれない。
が、日高サンはそんな想像をばっさり断ち切ってしまう。
生きものが生きるということは、種間の、そして同じ種同士でのすさまじい生存競争を経て、生き延びていくのである。まさしく命がけだ。「生物多様性」が豊かな状況は、この、あらゆるレベルでの生存競争の結果でしかない。激烈な競争としての生態系の複雑さ、そしてその頂点に人間がいることに、私たちは改めて考える必要があるだろう。
日高サンのエッセイは非常に読みやすい。そして奥が深い。簡単に読み終わるけれど、読後感は決して軽いものではない。むしろ考えてしまうことも多い。
が、その考え込むプロセスは、嫌なものではない。日高サンのすべての生きものを愛おしみ、その命を慈しむ気持ちに触れているからかもしれない。
日高サンのそのほかの著書。文庫で出版されているので、ぜひご一読を。タイトルもすごくかわいいです。
「春の数えかた」(新潮文庫、2005年)
「動物と人間の世界認識―イリュージョンなしに世界は見えない」 (ちくま学芸文庫、2007年)
「ネコはどうしてわがままか」(新潮文庫、2008年)
「セミたちと温暖化」 (新潮文庫、2009年)
著者:日高 敏隆
発行:新潮社 (2006年)