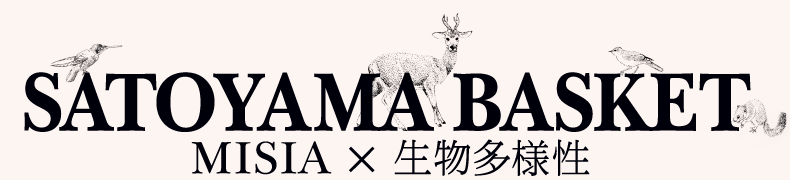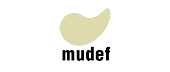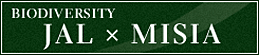今月の本:「いのちの食べかた」
作:森 達也
発行:イースト・プレス(2011年)
この本を読んで、しばらく呆然としていた。始業時間前だったけれど。
「生きることは、いのちを食べること」。
当たり前ではあるのだけど、私たちが口にする魚やお肉、野菜。すべて生きている。
食べものだけじゃない。
新薬開発に欠かせない動物実験、水を確保するためにダムを作る、経済開発目的で、海を埋め立てることで膨大な数の魚や微生物が犠牲になっている。畑で使われる殺虫剤。お米作りで使われる農薬が原因でトンボが見られなくなったとの話も、よく耳にしてきた。
食卓に並ぶ魚の切り身、大好きな焼き肉、ハンバーグ。
でも食卓に並ぶまでに命はどうやって奪われていくのだろう。そんな事実を、私たちはあまり考えない。その「考える」ことを放棄している姿勢が、作者である森達也さんによって指摘される。
森さんは、もともとテレビで多くのドキュメンタリー番組を制作されてきた。森さんが描く「と場」で、一日平均350頭の牛が、1200頭の豚が命を奪われ、細かくされたのちに、食卓へ向けて運び出されるプロセスが淡々と描かれる。その視覚イメージを喚起させる文章で、リアルに屠殺のプロセスが脳裏に浮かぶ。
だから手にした本を放り出したくなるかもしれない。
さらにこの本が指摘するのは、日本の食肉の歴史だ。私たちが今まで知ろうとしなかった、知っていても知らん顔をしてきた歴史だ。生物多様性は、「命のつながり」であり、命を奪い、食べていく、その果てしなき連鎖だということ。それにも関わらず、「知らない」ということで、軽んじられてきた、奪われる命の重み。
森さんは途中で、宮沢賢治の童話「よだかの星」の話を紹介する。醜いよだかが、殺生をしたくなくて、最後に星になってしまう物語だ。星になれない私たちができること。命を「いただく」こと、そのことを知り、考えることなんだと、森さんは繰り返し書いている。
その「知る」ことの重みに、呆然としてしまった。でも自分の中から、声が聞こえてきた。「生きること、命の重みを知ること」。
生きることは残酷だ。でもだからこそ、知る必要がある。